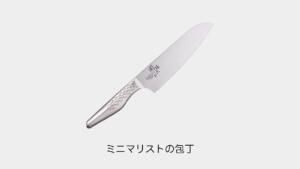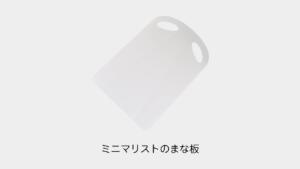食べ物を食べるためにはお箸やスプーン、ナイフ、フォークなどの道具が必要だ。
海外に住んでいるので初めはスプーン、ナイフ、フォークを試していたが
最終的にやはり使い慣れたお箸こそが一番コンパクトで洗いやすく、便利だという結論に達した。
- 日本人としては一番使いやすいのはお箸。
- 洗い物も少なくて済む。
基本的なお箸を選ぶコツは?
前提条件として箸を選ぶコツを書いておく。
サイズ
親指と人差し指を直角 に広げたときのそれぞれの指先を結んだ長さを一あたと呼ぶのですが、お箸は一あた半が良い。
※男性は23cm~24cm、女性は21.5cm~22.5cmくらい
形状
三角形、四角形、五角形、六角形、七角形、八角形、丸型、けずり、ハート側と様々な形状がありますが、
まず角があるお箸をがおすすめ。
さらにお箸は三本指で持つので、奇数角の方が持ちやすい。七角形辺りをすすめたい。
材質
黒檀、鉄木、紫檀、マラス、桑、山桜、栃、エゾ松、ヒノキ、杉と様々な材質があるが、少し重みがあるほうが持ちやすい。
なので比重の高い、黒檀が好まれる傾向にある。
箸の先端(喰い先)
箸は先端部分から劣化します。
また先端から3cmほどは、口触りにも影響するので、その部分にこだわっている箸がおすすめ。
ミニマリストのおすすめのお箸は?
使い慣れていて、洗い物も少ないお箸がベター。
携帯ができて、マイお箸になるとさらに良い。
こればっかりは毎日、一生使うものなので、いろいろ試して研究を重ねるしかない。
福井クラフト 箸
安価(620円)で、七角系で、先端がちゃんとしていて、食洗器OKのお箸は福井のクラフト箸。
まずはこの箸から、試して自分の好みを探ってみるもの良いだろう。
モンベル スタックイン 野箸

- コンパクトに収納でき、持ち運び持ちやすい。
- 木素材
- 見た目が良い。
- 価格が高い。
- 収納方法に慣れが必要
snow peak お箸
おすすめはスノーピーク製のもの。
1/2のサイズで折りたためて携帯も用意。
機能も改良を重ねていて使いやすい。
デメリットは素材が竹で、高価なところ。
まとめ
海外に暮らしてみて、やっぱりお箸が便利だと理解した。
考えてみたら、軽くてコンパクトで、経済的で本当に優れた道具だと思う。
一生使う道具は、自分が何が好みなのか?
いろいろ試して、記録を付けて研究するべきである。
理想の箸が分かれば、大切な食事の時間がより楽しくなる。
ミニマリストのお箸に関するよくある質問
- ミニマリスト向けのお箸の特徴は何であるか?
-
ミニマリスト向けのお箸の特徴は、シンプルなデザイン、高品質の素材、そして耐久性があることである。
- お箸選びでミニマリストにとって重要なポイントは何であるか?
-
お箸選びでミニマリストにとって重要なポイントは、シンプルなデザイン、素材の質、耐久性、そして使いやすさである。
- ミニマリストに適したお箸の素材は何であるか?
-
ミニマリストに適したお箸の素材は、天然木や竹、ステンレススチール、チタンなど、高品質で耐久性があるものが望ましい。
- ミニマリスト向けのお箸のデザインでおすすめなものは何であるか?
-
ミニマリスト向けのお箸のデザインでおすすめなものは、シンプルで無駄のない形状、モノトーンや自然な色合いが好ましい。
- ミニマリストにおすすめのお箸のブランドは何であるか?
-
ミニマリストにおすすめのお箸のブランドは、シンプルで機能的なデザインを提供するブランドである。例えば、無印良品、菊渕(Kikubuchi)、おおいた竹箸などが適している。